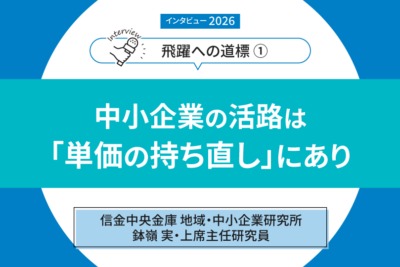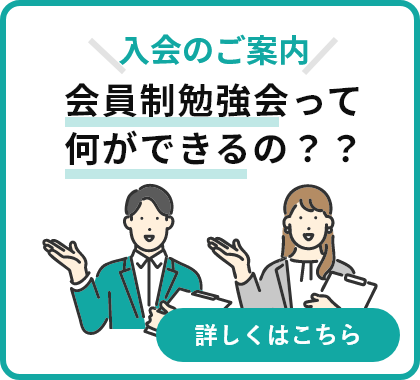「誰かアイデアを考えてくれないかな」「誰かプレゼン資料を作ってくれないかな」。このような日常の何気ない願望の多くが今、手軽に実現する時代になっています。ちょっとした「つぶやき」を叶えてくれる存在、それこそが生成AI(Artificial Intelligence=人工知能)です。生成AI基盤技術の開発を支援する「GENIAC」(ジーニアック/Generative AI Accelerator Challenge)プロジェクトの一環として、生成AIの社会実装(=研究成果を実社会で役立てる)促進を目的にアプリケーション開発に特化した懸賞金制度「GENIAC-PRIZE」が進行中です。生成AIを活用した解決が期待される3領域の4テーマについて開発を促すもので、懸賞金総額は約8億円です。あなたのひらめきが生成AIの活用領域を広げるかもしれない。そんな可能性を秘めたGENIAC-PRIZEプロジェクトの狙いや、生成AIをとりまく話題について、同プロジェクトを国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構」(NEDO)とともに主催する経済産業省の担当室長にインタビューしました。記事の後半では、AIにまつわる国内の主な動向とGENIAC-PRIZEプロジェクトの概要なども紹介しています。AIの研究開発に携わっている方も、そうでない方も、ぜひAIの世界を楽しんでください。
経済産業省の渡辺琢也・AI産業戦略室長インタビュー
出でよ!最新テクノロジーのトップランナー
今回の懸賞金活用型プロジェクト「GENIAC-PRIZE」は、経済産業省とNEDOによって行われています。経済産業省で同プロジェクトを所管しているAI産業戦略室の渡辺琢也室長に、生成AIをとりまく話題も含め、お話を伺いました。
―― GENIAC-PRIZEプロジェクトの前段として、GENIACプロジェクトの活動内容を教えてください。
GENIACというプロジェクトは2024年2月に立ち上げました。生成AIの「エンジン」にあたる基盤モデルの開発力強化を目的としています。生成AIという、世の中を大きく変えるかもしれないテクノロジーが出てきて、AIをふんだんに使っていくことが非常に重要になっています。しかしAIを使うだけではなく、作っていくことも必要です。日本として、きちんと生成AIの開発能力を向上させていくという目的でGENIACというプロジェクトを立ち上げました。
GENIACの取組により、生成AI開発に手ごたえ
GENIACは、大きく三つのメニューで構成されています。一つは、計算資源の調達支援です。生成AIを作るためには計算資源が必要ですが、計算資源というのは、物理的にも金銭的にも、確保することが非常に難しいものです。この計算資源をきちんと調達できるように支援しています。
二つ目は、AIを作るうえで欠かせない大量のデータの確保です。特定の領域に特化したユニークなデータは、インターネットにアクセスすれば簡単に手に入るというものではありませんので、AIの開発者が使えるようにすることが必要です。さらに三つ目は関係者同士のコミュニケーション、ネットワーキングの支援です。
世界をリードするような汎用的なAIというと、アメリカや中国といったビッグプレーヤーが提供しているものになります。しかしGENIACの取組を通じて、日本も、例えば、ある領域、ある性能においては、非常に良質なAIを作れるようになってきましたし、その数も増えてきたという手ごたえを感じています。
キーワード
計算資源
高性能コンピューターの開発に重要となる、コンピューターが計算処理を行うために必要なリソースのこと。GPUやCPU、メモリ、ストレージなどを指し、基盤モデル開発に不可欠である。日本は計算資源の整備の遅れが指摘されているが、GENIACプロジェクトが計算資源の調達支援を手掛けるなど、対策が進みつつある。
基盤モデル(ファウンデーションモデル)
2021年に、米・スタンフォード大学の研究者らによって命名された。大量且つ多様なデータによる学習や訓練に基づいて、様々なタスクに適応できる仕組みのことを指す。生成AI開発におけるコア(核)となる技術基盤であり、基盤モデルの開発力が生成AIの開発力を左右すると言われている。
GENIAC-PRIZEの目的はアプリ開発の促進
AI開発のための環境整備・開発促進、といった活動をさらに加速させるには、AIを使っていくことが必要です。事業者が保有するデータやナレッジというのは、誰もがアクセスできるものではなく、その事業者固有のものですね。そのようなノウハウなりデータをベースとしてAIを作っていくためには、AIの作り手だけが頑張るのではなくて、AIを使っていくという動きとセットで進めていく必要があるという認識です。
そこで今回GENIACの中で、GENIAC-PRIZEという枠組みを新たに設けました。GENIACで開発に取り組んでいる基盤モデルというのは、生成AIの「エンジン」です。エンジンが無いと車は走りませんので、非常に重要なパーツです。しかしエンジンだけで車を作ることは出来ません。エンジンをコアにして、しっかりと使うことが出来るようアプリケーションの形にしていく必要があるでしょう。つまり、GENIAC-PRIZEの狙いは、アプリケーション開発ということになります。
今回、GENIAC-PRIZEでは開発テーマを四つ掲げています。各テーマを具体的なニーズに落とし込みながら、実際に生成AIを使うためのアプリケーションを開発して、そして検証していく。これによって、エンジンの開発と、実際に生成AIを使うということを同時に進められると考えています。このような一連の営みを全国各地、さらにはいろいろな業種で促していくために設けた枠組みがGENIAC-PRIZEである、ということになります。
―― GENIAC-PRIZE は、NEDO懸賞金活用型プログラムの枠組みの一つとして実施されています。官公庁による支援策としては、補助金・助成金の交付という形もありますが、今回、懸賞金方式で実施されている狙いについて、教えてください。
研究開発のための補助金という形は、例えば先ほど申し上げたエンジンを作るような場合には有効になってくるかと思います。エンジン開発は非常に多額な研究開発投資が必要ですので、あらかじめ研究開発の支援対象となる事業者を決めた上で研究開発費用を支援(補助金・助成金を交付)し、研究開発を促すというものです。これは、政府が研究開発を進める場合の、非常にオーソドックスなパターンですね。
インセンティブ方式で盛り上げる!
今回GENIAC-PRIZEが対象としているのは生成AIのアプリケーション開発です。エンジン開発とアプリケーション開発では、いくつか異なる点があります。
まずはコスト面です。もちろん、アプリケーション開発にも費用はかかりますが、エンジン開発ほど多くの費用がかかるわけではありません。
また、エンジンを作る人となると、かなり限られてくると思いますが、アプリケーションを作る、それを使っていくとなると、ほぼ全事業者が該当すると言っても過言ではありません。その場合、あらかじめ支援対象者を絞り込んで開発を促すよりも、実際に出てきた良い成果に対して懸賞金というインセンティブを与えることで、多くの方にプロジェクトに参加していただく枠組みの方が適切だろうと考えました。また、成果に応じてインセンティブを与えるほうがフェアだろうという点も加味しました。
エンジン開発(基盤モデル開発)の支援に要する費用と比べると予算が抑えられること、あらゆる人にアプリケーション開発に挑戦していただきたいということ、そして成果に対しインセンティブを与えるという公平さ。大きくこの三つの観点が、懸賞金方式が合理的だろうと判断した理由です。
あとは、なんといっても、コンテスト型は多くの方のチャレンジ意欲を掻き立てますよね。アプリケーション開発と利用という、すべての方が参加しうる枠組みの中で賞金型のプログラムを実施することによって、日本全体を盛り上げたいという狙いもあります。
―― GENIAC-PRIZEの募集テーマは4テーマです。それぞれ、実生活で想定される場面を、ご紹介ください。また、4テーマが選定された理由を教えてください。
生成AI×物づくり、狙うはグローバル展開
まず一つは、製造業における暗黙知の形式知化(「5.2 四つのテーマと懸賞金額」の領域1参照)、その上で、いかにAI化していくかということです。日本は非常に製造業が強い国ですから、その強い製造業をAI化する作業は、うまくいけばグローバルに展開する可能性が出てきます。一方で、物づくりの現場では熟練労働者がリタイアを迎えていきますし、生産労働人口も減っていきます。物づくりにおいて、適切に出来上がったものか欠陥品かの判定、効率的な設計といったものを、特定の熟練労働者に依存していた部分があるかもしれませんが、そういった部分をAIという形にし、高い生産性を後世に残していく必要があります。それができれば、先ほども申し上げた通り、物づくりにおいて日本は国際競争力があるわけですから、グローバルに展開させる可能性が出てきます。
今や必須のカスタマーサポート
二つ目はカスタマーサポートです。例えば、官公庁は国民の皆様からいろいろな質問を受けて、それにお答えしています。また、製品やサービスを提供されている方も、外部からの問い合わせ対応というのは必ず発生します。今回、生成AIのアプリケーション開発を様々な地域・業種に取り組んでいただきたいという狙いがありますので、みんなが取り組めるテーマは何だろうと考えたときに、今やあらゆる組織に置かれているカスタマーサポートだということになりました。
カスタマーサポートは、外部との積極的なコミュニケーションが求められており、担当者がマニュアルも参考にしながら外部との接点役を果たしているのだろうと思います。同時に、生産性向上という切実なニーズもありますので、生成AIを活用して効率よく外部対応をこなしていく必要性もあるだろうと考えています。
まずは官公庁が率先して活用
三つ目は、官公庁の審査業務です。皆さんに「生成AIを使ってください」と言う以上、まずは官公庁が率先的に活用すべきですね。官公庁は審査業務が多いですが、より具体的なイメージを持っていただくために、経済産業省の外局である特許庁が行っている特許審査業務をモデルとして掲げました。特許審査は、新規性、類似性を人間が審査していますが、これをAIが効率的にやるという活用場面が考えられます。
欠かせないリスク対応技術
最後四つ目は、これまでと少々毛色が違いますが、安全性の向上に役立つ技術ということになります。生成AIについては、例えば、「ハルシネーション」(=AIが事実とは異なる内容や、学習データに存在しない内容を生成してしまう現象)や、画像や動画も生成できてしまう「ディープフェイク」の悪用、個人情報の流出・漏洩…といったリスクが懸念されます。生成AIアプリケーションを世の中に普及し、安心して使っていただくため、リスク対応技術という幅広いテーマを設けました。
―― GENIAC-PRIZEは開発を競うコンテストですが、生成AIの利活用という観点では、どのような意義を持つのでしょうか。
開発と利活用は表裏一体
AIを作る・開発するということは、スーパーコンピューターを使ってデータをAIに学習させる作業です。ある業務なり、ある価値を生み出すとき、このデータはどのように使われるのかということを考えなければ、意味がありませんね。つまり、様々なデータをAIに変えていく上で、データの利活用とセットで考えなければ「使えるAI」は作れませんので、AIを作ることと使うことは表裏一体だと考えています。
利活用を進めることで新しいデータが生まれ、AIが使われることで使われ方が学習されていきます。このように、AI開発というのは固定的なものが世にリリースされるということではなく、新しいフィードバックを得ながら進化していく、AIが賢くなっていくということでもあります。どんどんAIを使っていただきたいと申し上げてきたのは、このような背景があるためです。
―― GENIAC-PRIZEプロジェクトの開発成果は、今後どのようにして、実社会で使われるようになるのでしょうか。
優れた成果は公開されるため、例えば同業種の方や同じ地域の方の中には「そういう使い方があるのか」と気づく方も多いでしょうし、自分たちも作ってみよう、使ってみようという波及効果も生まれるのではないかと考えています。
今回、たくさんの応募が期待されますが、表彰式(2026年3月予定)以降、エントリーいただいたサービスや事例を経済産業省の媒体を通じて皆様に知っていただくのはもちろん、マスメディアの力も借りながら全国で周知活動を行い、「使ってみようかな」という動きを促していきたいと考えています。
―― GENIAC-PRIZEプロジェクトへのチャレンジを迷っている方もいるかもしれません。そのような方々が一歩踏み出せるようなメッセージを、最後にお願いします。
アプリ開発に参加し、生成AI普及のけん引役に
生成AIというのは、一部の人が作るとか、一部の人が使うというものではないと思います。生成AIは、インターネットやスマホに次ぐような、人間の生活や事業活動を豊かにして生産性を向上させる画期的なテクノロジーとなるでしょう。AIは自分には関係ないとか、自分は使うだけということではなく、もちろんレベルの違いはあるにせよ、あらゆる人たちが(生成AIアプリケーションの)創出に関与することが非常に大事だと思っています。新しいテクノロジーを作って使う、ということを広げていきたいわけですが、GENIAC-PRIZEに応募される方には、その先陣を切っていただく、お手本になっていただくことを大いに期待しています。我こそはというアイデアがある方には、ぜひ応募いただいて、日本の先陣を切っていただきたいと思っています。
※一般社団法人九州広域行政事務支援機構はGENIAC-PRIZEの協力企業です。
01 AI、生成AIをとりまく国内の動き
GENIAC-PRIZEプロジェクトをご紹介する前に、AIをとりまく国内の主な動きをご紹介します。まず政府などの取組を、続いて民間の動向を見てみましょう。
「官」の取組
AI戦略会議(イノベーション政策強化推進のための有識者会議)
政府は2023年5月、大学の研究者らをメンバーとするAI戦略会議を設置しました。実社会でのAI技術の活用推進、AIリスクの抑制、AI開発力の強化等のテーマについて議論を重ねています。また、AI戦略会議のもとには、AIに関する法規制のあり方を検討する有識者会議であるAI制度研究会が設置されています。
AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)
イノベーションを促進しつつ、リスクに適切に対応することを目的として、2025年6月に施行されました。国内では初のAIに関する法律となります。研究開発の推進、AIに関する国際的な規範策定への参画、国際規範に即した指針の整備、AI人材の確保等に関する内容が盛り込まれています。同法に基づき、AIに関する具体的な取組を加速すべく、内閣総理大臣を本部長とし全閣僚が参加する「AI戦略本部」が今秋までに設置される見込みで、AI政策に関する国の「司令塔」の役割を果たすことになります。
AI 事業者ガイドライン(第 1.1 版)
AIの安全安心な活用を促進し、イノベーションとリスク緩和を両立させるため、AI開発者・提供者・利用者の自主的な取組を後押しする統一的な指針として2025年3月に公表されました。人間中心の基本理念に基づき、「人間中心」「安全性」「公平性」「透明性」など10の共通の指針を提示し、特に高度なAIシステム向けにも指針を定めています。その実践として、リスクに応じたアジャイル・ガバナンス(技術の進化や社会状況にあわせて柔軟かつ迅速に対応できるルールづくりの考え方)の構築を促し、国際的な議論とも協調する非拘束的なソフトロー(法的な強制力はないものの、事業者の自主的な行動を促す指針や基準のこと)として策定されました。
AIセーフティ・インスティテュート(AISI)
AIの安全性に関する評価手法や基準の検討などを行うため、2024年2月に独立行政法人情報処理推進機構(IPA)内に設置されました。AISIは、AIの安全性に関する知見のハブとして、米英など国際的なパートナーと連携し、相互運用可能な生成AIの安全性評価手法の確立を目指しています。
「民」の取組
民間においては、大企業からスタートアップ企業まで、実に多種多様な取組・研究開発が行われています。経済産業省「GENIACの取組について」(2025年4月)から、一例を紹介します。
| GPT-3.5(=OpenAIが開発した言語処理モデル)級の小型で効率的なモデルを開発 | Sakana AI株式会社 |
| 日本語と画像理解に関する世界最高レベル性能のVLM(=文字情報と画像・動画といった視覚的な情報の融合により、複雑なタスクに対応できる技術)開発 | Turing株式会社 |
| 実写動画・アニメ動画作成に向けた動画生成AIモデルの開発 | 株式会社AIdeaLab |
| AI創薬の実現に向けた分子情報に特化した基盤モデルの開発 | SyntheticGestalt株式会社 |
| 都市のリアルタイム情報提供を可能とするマルチモーダル基盤モデル(=文章・画像・音声など複数の情報を同時に処理し、総合的に判断・出力するAI技術)の開発 | ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 |
| 世界最高性能の日本語言語処理技術によるパーソナルAI(=個人ごとに最適化されたAI)の開発 | 株式会社オルツ |
02 一大プロジェクト「GENIAC」
官民挙げての一大プロジェクトと言えるのが、経済産業省とNEDOが、国内の基盤モデル開発力を強化する目的で2024年2月に立ち上げたGENIACです。生成AI開発において重要なリソースの「3点セット」である計算資源、データ、ナレッジに関する支援を行っています。具体的には、計算資源の利用料の補助、知見共有のためのコミュニティ運営、生成AIおよび生成AI開発に欠かせない大量のデータの利活用に向けた実証支援(=効果を検証するための実験などを支援すること)、基盤モデルを開発する側と利活用する側の交流を促すマッチングイベント開催などを行っています。GENIACによる計算資源の調達支援を受けた開発が、すでに様々な成果を生み出していることは、先にご紹介した通りです。
03 「作る技術」と「使う技術」
GENIAC-PRIZEの内容に関する説明は「5.GENIAC-PRIZEプロジェクトの概要」を、ご参照ください。ここでは、GENIACとGENIAC-PRIZEの役割・立ち位置を、渡辺室長がインタビューでも説明された車の開発事例になぞらえて整理したいと思います。
GENIAC:生成AIを「作る技術」を支援
GENIACは、車にたとえるとエンジン開発を支援しているプロジェクトです。車を構成するパーツはたくさんありますが、車の性能の決め手となるのはエンジンでしょう。生成AI開発で言うと、その性能の決め手となるのが「基盤モデル」にあたります。2024年2月の立ち上げ以来、生成AIの中核をなす基盤モデルの開発を後押しする様々な活動を進めています。
GENIAC-PRIZE:生成AIを「使う技術」を支援
GENIACプロジェクトによって、基盤モデルの開発については一定の成果が出てきました。車のエンジン開発が進んだ状態と言えます。ところで、エンジンは車の中核部分ではありますが、エンジン「だけ」があっても動きません。エンジンの周辺パーツや、車を運転・利用する人がなければ、車は動くことのない単なる鉄の塊です。
そこで、エンジン製造をさらに進めて、実際に車を乗りこなすための技術開発を後押しするのがGENIAC-PRIZEプロジェクトです。生成AIを実際に使いこなすためのアプリケーション(アプリ)開発を促す取組と考えると分かりやすいでしょう。生成AIアプリがあって初めて、生成AIは文章、画像、音楽、アイデアなど多様なコンテンツを生み出すことが可能となるのです。
この2つのプロジェクトが連携することで、日本の生成AIに関する技術開発から社会実装まで、一貫した推進体制が構築されることになります。
04 課題への対応、待ったなし
AI開発は、国家が戦略やインフラ、ルール形成を通じて基盤を整備し、企業がその上で具体的な技術開発とサービス展開をけん引するという、国家と企業双方の協力関係によって進められています。国内でも同様な構図のもと、これまでご紹介したような取組が進んでいます。一方でAIに関するリスクや、AIを不安視する声などへの対応といった課題も浮き彫りになっており、迅速な対応が求められています。
AI 戦略会議・AI制度研究会が議論を重ね、2025年2月に公表した「中間とりまとめ」には、以下の言及があります。
①AIは我が国の発展に大きく寄与する可能性がある一方、様々なリスクが顕在化している。
②AIに対する不安の声が多く、諸外国と比べても開発・活用が進んでいないとの指摘がある。
③AIの透明性など、適正性を確保してAIの開発・活用を進める必要がある。
まず①については、AIを用いた誤・偽情報の作成や拡散、また、そういった情報が拡散されることによる情報操作などのリスクが挙げられます。「中間とりまとめ」は、サイバー攻撃などにAIが使用される安全保障上のリスクにも言及しています。
②については、AIのリスクや安全性に関する意識調査(国際比較)が掲載されています。下のグラフをご覧ください。それによると、以下の事柄が読み取れます。
✔ 日本は米国と比較して、「品質の不安定さ」「プロセスのブラックボックス化」「フェイクコンテンツ」に不安を感じている企業が多く、AIリスクへのガバナンス(適切に管理する仕組み)の取組をする企業が少ない。
✔ 日本では、「現在の規則や法律でAIを安全に利用できる」と思う回答者は13%と、調査対象国の中で最も低い。

また③に関しては、国内調査(下のグラフ)によると、企業に求めたいことは「顧客データの安全性とプライバシー保護の強化」が66%と最多、政府には「AIの悪用や犯罪に対する法的対策の強化」を求める声が66%で最も多いことが分かります。

AI法でイノベーション促進とリスク対応の両立が図られているのは、上記のような背景もあります。
05 GENIAC-PRIZEプロジェクトの概要
応募に際しての提案書の具体的なフォーマット、デモ動画の技術的要件、各領域における詳細な審査基準や評価方法、スケジュール、説明会動画、よくある質問などは、GENIAC-PRIZEプロジェクトの公式サイトでダウンロードまたは閲覧可能です。応募を検討される場合は、必ず参照してください。

5-1 プロジェクトの狙い
では、いよいよ、GENIAC-PRIZEプロジェクトの中身を見ていきましょう。
GENIAC-PRIZEプロジェクトは、生成AIの実導入へ向けニーズをきめ細かく満たすためには、さらなる開発が必要な官民の領域がある、との認識に基づくものです。今回、生成AIサービスによる解決が望まれる4テーマを設定し、各テーマにおける具体的なニーズに基づいて開発・実証した生成AIアプリケーションと、その実証成果を応募してもらい、成果に応じた懸賞金を授与します。これにより、様々な地域や業種における企業などによる生成AIサービスの開発と実導入の促進を目指します。
経済産業省の「GENIACの取組について」では、生産性成長率と実質GDP成長率に一定の相関関係があり(下のグラフ)、生成AIを活用して各産業の生産性を押し上げることにより、我が国の経済成長をけん引し得るとしています。したがって、AIの技術開発・実証を競い合うことは、様々な産業課題の解決、ひいては生産性向上、そして経済成長へとつながる好循環を生み出すことが期待されます。

5-2 4つのテーマと懸賞金額
GENIAC-PRIZEプロジェクトは、「NEDO懸賞金活用型プログラム」に基づき、技術課題や社会課題の解決に貢献する多様なシーズや解決策をコンテスト形式で募り、成績上位者に懸賞金を贈る方式で実施されます。本プロジェクトでは、生成AIによる解決が期待される3領域4テーマが設定され、懸賞金総額は約8億円に上ります。設定されたテーマの概要と懸賞金額は以下の通りです。
領域1:国産基盤モデルなどを活用した社会課題解決AIエージェント開発
| Ⅰ. 製造業の暗黙知の形式知化 個人が蓄積してきた経験やノウハウなど、言語化して伝承することが困難な知識を、生成AIを利活用して言語や数式、図表などで表現できる知識に変換する。日本の製造業は高い技術力を有しているものの、熟練工が長年の経験から得た「暗黙知」が現場の高い品質や生産性を支えていることも多く、将来失われるリスクがある。形式知への変換により技術伝承や生産性向上も期待される。 |
| Ⅱ. カスタマーサポートの生産性向上 カスタマーサポートでは、高い離職率や採用難などの要因により深刻な人材不足が生じており、カスタマーサポートの生産性向上が急務となっていることから、生成AIの活用に対する意識が高まっている。生成AIにはハルシネーションや安全性に関する懸念もあるが、業務プロセスの見直しなどによって、その活用余地は広がる。効果的な活用により、生産性向上と顧客対応品質の向上が期待される。 |

(以降の図表の出典は、いずれもGENIAC-PRIZEプロジェクトの公式サイト)
領域2:官公庁などにおける審査業務等の効率化に資する生成AI開発
| 官公庁の主要業務の一つである審査業務を多く抱える現場では、審査業務に対する負担感の増加、審査ノウハウの属人化といった課題を抱えており、審査業務の効率化は官公庁に共通するニーズといえる。効率化や生産性向上を実現する生成AIを適用し、職員のアシスタントとして機能させることで、審査業務の効率化が図られ、職員がより付加価値の高い業務に集中できるため労働生産性も向上する。 |

領域3:生成AIの安全性確保に向けたリスク探索およびリスク低減技術の開発
| 生成AIのリスクの観点においては、具体的にどのようなリスクが生じうるか、国際的にも共通の理解が醸成されているわけではない。例えばハルシネーション、偽・誤情報等の流通・拡散、知的財産権などの侵害は、社会的に認識されているものの、リスクを網羅的に示すことは困難である。本事業を通じて、社会全体として生成AIにより生じ得るリスクを認識するとともに、リスクを低減する技術開発を促進することで、わが国における生成AIの受容性を高め、生成AIの利活用・社会実装を後押しする。 |

※領域3は「トライアル審査」が設けられています。同審査にて高評価を得た応募者(複数団体の可能性あり)に対しては、本審査とは別に最低500万円の懸賞金が分配されます。なお、トライアル審査に応募せずとも本審査へ応募することは可能です。
5-3 応募の主な条件等
領域1
| 応募資格 | ユーザー:法人 開発者:法人※、個人 ・原則ユーザーからの応募 ・ユーザー/開発者で組んで応募も可 |
| 応募内容 | ・提案書 ・デモ動画 |
| 国産基盤モデル | 開発・実証は必須 |
| 主なスケジュール | ・応募期間:2025年9月末まで ・プロトタイプ開発、実証期間:2025年12月末まで |
領域2
| 応募資格 | 法人のみ |
| 応募内容 | ・提案書 ・プロトタイプ(=試作版のソフトウェア) |
| 国産基盤モデル | 活用すれば加点 |
| 主なスケジュール | プロトタイプおよび提案書の 応募(提出)締切:2025年12月上旬まで |
領域3
| 応募資格 | 法人のみ |
| 応募内容 | ・提案書 ・プロトタイプ/プロダクト (※リスク低減の可能性を示すこと) |
| 国産基盤モデル | 活用の有無は問わない |
| 主なスケジュール | ・トライアル審査応募期間:2025年7月末まで ・本審査応募期間:2025年12月末まで |
※応募(エントリー)締め切り日は延長の可能性があります。
法人:日本国内の法人(企業、大学、国研など)および団体(官公庁、地方公共団体など)
ユーザー:AI事業者ガイドラインで規定しているAI利用者(日本国内の法人(企業、大学、国研など)および団体(官公庁、地方公共団体など))。原則、本事業の応募者とする。
開発者:AI事業者ガイドラインで規定しているAI開発者およびAI提供者(日本国内の法人(企業、大学、国研など)、団体(官公庁、地方公共団体など))および個人。
5-4 今後の主な予定
✔ 表彰式:2026年3月
✔ 表彰式後の成果普及イベント:2026年3月末以降
✔ 懸賞金交付:2026年5月

5-5 よくある質問
領域1
- 国産基盤モデル以外を活用した提案も可能か。
-
可能です。ただし、国産基盤モデルの開発・実証は必須で、活用しない場合は不採用理由を提案書で明確にしてください。
領域2
- 開発した技術を用いて官公庁以外の顧客向けにサービスを開発してよいか。
-
開発した技術の帰属は事業者にあるため、当該技術をサービス開発に活用しても構いません。
領域3
- 応募にあたって定量的な結果や評価指標を示す必要があるか。
-
可能な限り客観的に審査を行うことができるよう、定量的な成果や評価指標を用いていただくことが望ましいです。定性的である場合であっても可能な限り客観性や具体性のある基準を設けることを推奨します。
06 まとめ
文部科学省の「令和6年版 科学技術・イノベーション白書」などの資料によると、「人工知能(AI)」という言葉は、1956年にダートマス会議で初めて使用されたといいます。それから69年が経ちました。AIを巡る状況は大きく変化し、特に生成AIの開発競争は国際的に激しさを増しています。しかし、その技術はいまだ発展途上にあり、専門家でさえ今後の動向を予測することは困難です。
そのような中、生成AIの社会実装の促進を目的として、経済産業省とNEDOが実施しているプロジェクトがGENIAC-PRIZEです。このプロジェクトへの「誰かの挑戦」「一つの挑戦」によって、AIの世界を変えたのはGENIAC-PRIZEプロジェクトだったねと、のちに語られる時代が来るかもしれません。そう考えると、わくわくしますね。 「…という感じの記事を書いてくれる人がいないかな」。えっ?つぶやきが聞こえましたか?そういえば、生成AIは、人が書いたような自然な文章を作成することができるのでしたね。申し遅れました。この記事を書いたのは――。
▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼
▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局
ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!