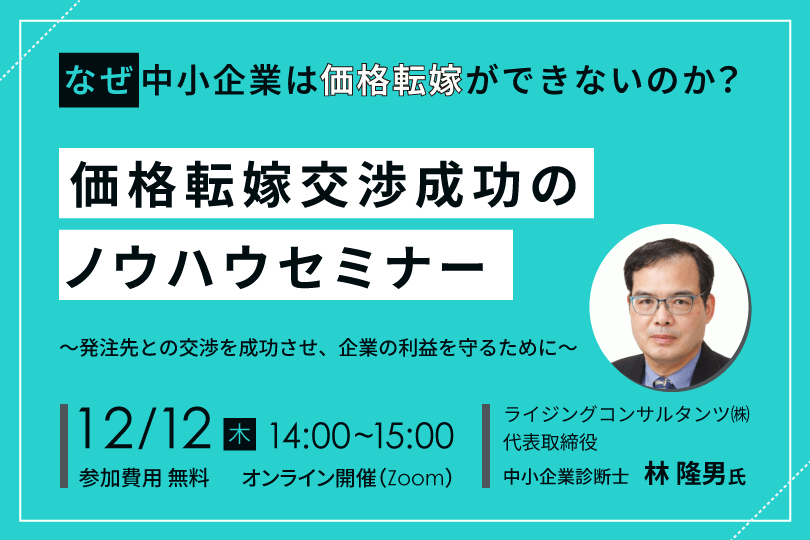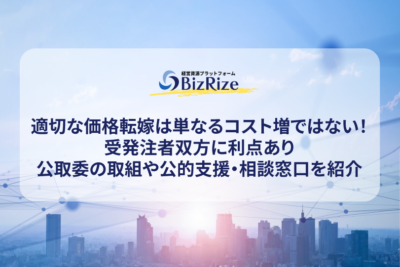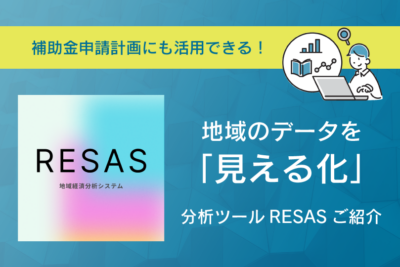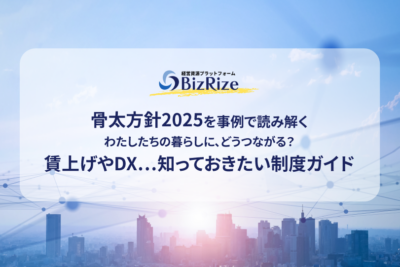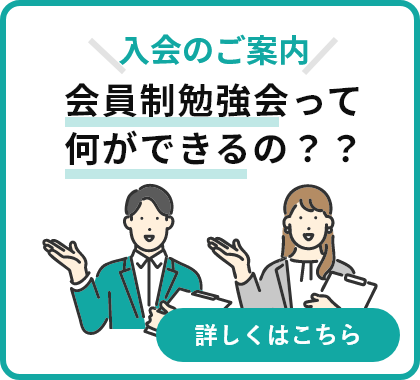昨今、「適切な価格転嫁」の必要性が叫ばれています。2025年5月には改正下請法が成立し(2026年1月施行)、賃上げ原資の確保やサプライチェーン全体の健全性確保を狙った環境整備が進められています。
しかし現場では、重要性を認識しながらも「適正な転嫁ができない」「どう交渉すればよいか分からない」という悩みが依然として多く聞かれます。
価格転嫁は一部企業の努力目標ではなく、日本経済全体の持続可能性に直結する社会課題です。だからこそ、制度や指針だけで終わらせず、実務の現場で困ったときに頼れる相談窓口や支援制度があることも知っておく必要があります。 本記事では、価格転嫁に関する課題とともに、実際に活用できる支援情報もご紹介しますので、ぜひ活用してください。
目次
- 公的資料での言及
- 1.1 2025年版中小企業白書
- 1.2 骨太方針2025
- 法的な根拠
- 公正取引委員会の取組
- 3.1 労務費転嫁交渉指針の策定
- 3.2 調査の実施
- 3.3 現場の声
- 3.4 価格交渉の申込様式
- 相談窓口などの一覧
- 適切に行われない場合の弊害
- 5.1 中小企業に忍び寄る「疲弊と停滞」
- 5.2 大企業の競争力低下を招く可能性
- 5.3 まとめ-適切な価格転嫁が促す共創
01 公的資料での言及
適切な価格転嫁の必要性について、公的資料ではどのように言及されているのか、まずは二つの事例を読み解いてみましょう。
1.1 2025年版中小企業白書
2025年版中小企業白書では、「適切な価格転嫁」の重要性が明確に示されています。物価や人件費の上昇、人手不足などでコスト削減には限界があり、付加価値や労働生産性を高めるための経営転換が不可欠としています。
また、中小企業が賃上げ余力を確保するためには、営業利益を高めることが不可欠であり、その鍵となるのが「高水準の価格転嫁の実現」であると指摘。企業間取引の適正化に向けた取組として、「パートナーシップ構築宣言」や「団体協約制度」にも言及しており、適正な価格設定は、大企業と中小企業の共存共栄を支える重要な仕組みであると強調しています。
下のグラフは、2022年から2024年におけるコスト全般および各コストの変動に対する価格転嫁率の推移を見たものです。各コストの転嫁率は上昇傾向であり、コスト全般の転嫁率は直近で5割程度まで上昇していますが、白書は「更なる価格転嫁の実現が期待される」としています。

1.2 骨太方針2025
骨太方針2025では、「物価上昇を上回る賃上げ」の定着を最重要課題の一つと位置づけ、 その実現に向けて「価格転嫁・取引の適正化」を明確に掲げています。中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しするには、官公需(国や地方公共団体等が、物品を購入したりサービスの提供を受けたり、工事を発注したりすること)への対応も含めた徹底した価格転嫁の推進が不可欠である点にも言及しています。また、生産性向上など他施策との連携により、企業が持続的に利益を上げ、投資、賃上げ、変化への対応などを実現できるよう総合的な経営基盤の底上げを図る必要性も指摘しています。
02 法的な根拠
適切な価格転嫁の推進は政府挙げての取り組みです。公正取引委員会、中小企業庁、経済産業省をはじめとした関係機関・組織がかかわっています。中でもそれらの中核であり、「法の番人」としての役割を担うのが公正取引委員会です。
公正取引委員会が「適切な価格転嫁」を推進する背景には、主に以下の法的な根拠と役割があります。
根拠1:独占禁止法(優越的地位の濫用)
公正取引委員会は独占禁止法の所管官庁です。独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする法律であり、「優越的地位の濫用」という禁止行為が定められています。
「優越的地位の濫用」とは、取引上の地位が相手方に対し優越している事業者(親事業者など)が、その優越した地位を利用して、相手方に対し正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為を指します。
独占禁止法の「よくある質問コーナー」Q20で、下記①と②に該当する行為が独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の一つに該当するおそれがあることを明示しています。
| ① | 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと |
| ② | 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと |
具体的な行為としては、発注者による次のような行為が優越的地位の濫用として問題となる可能性があります。
- 取引の相手方からの価格交渉の求めに、正当な理由なく応じないこと。
- コスト上昇を理由とした価格交渉を行った下請事業者に対して、取引数量の削減や取引停止といった不利益な取扱いをすること。
このように公正取引委員会は、独占禁止法の優越的地位の濫用の規定を適用し、不当な価格転嫁拒否や交渉拒否を規制することで、適切な価格転嫁を間接的に推進しています。
根拠2:下請法(下請代金支払遅延等防止法)
下請法は、独占禁止法の特別法的な位置づけであり、親事業者と下請事業者間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを目的としています。公正取引委員会と中小企業庁が所管しています。
親事業者の義務と禁止行為が具体的に定められている下請法は、2025年5月に改正下請法が成立し、適切な価格転嫁を実現するための大きな転換点となりました。特に注目すべきは、「協議を適切に行わない代金額の決定」が明示的に禁止された点です。これは単なる法規制の強化にとどまらず、発注側と受注側が対等な立場で向き合い、建設的な対話を行うための土台が法的に整備されたことを意味します。
また、改正下請法では、以下の見直しも盛り込まれています。
- 手形払等の原則禁止:手形による支払いは、中小企業の資金繰りの負担となるため
- 適用対象の拡大:より広範な取引における価格転嫁を促進するため
- 「下請」等の用語変更:「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」へと見直します。これは、発注者と受注者が対等な関係で取引を行うという、今回の法改正の趣旨を端的に示すものです。
以上のことから、公正取引委員会が適切な価格転嫁を推進する主な目的は、次のようにまとめることができます。
| 法律 | 規制範囲 | 趣旨・目的 |
| 独占禁止法 | 広範な規制 | 「優越的地位の濫用」規制を通じて、一方的・不当な価格決定や交渉拒否を是正する。 |
| 下請法 | 下請取引に特化した具体的な規制 | 改正法で新たに導入された「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」などの規定を執行することで、委託事業者と受託事業者間の公正な取引を確保し、価格転嫁を直接的に促す。 |
適切な価格転嫁は、法律で直接的に規定されているわけではありませんが、独禁法の目的である公正な競争の維持や、優越的地位の濫用の防止、そして下請法による下請事業者の保護といった、公正取引委員会が担う役割の延長線上に位置づけられる、非常に重要な課題だと言えます。
03 公正取引委員会の取組
このように、適切な価格転嫁の推進の中核を担う公正取引委員会は、様々な取組を行っています。主なものを紹介します。
3.1 労務費転嫁交渉指針の策定
内閣官房との連名で2023年11月に公表しました。労務費の転嫁に関して発注者と受注者が採るべき行動/求められる行動を全部で12の「行動指針」としてまとめたものです(下の表)。この指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会が独占禁止法および下請法に基づき厳正に対処することを明記しました。他方、発注者としての行動を全て適切に行っている場合は、取引当事者間で十分に協議が行われたものとして、通常は独占禁止法および下請法上の問題が生じない旨も明記しました。
発注者として採るべき行動/求められる行動の主な内容
| 行動① | 本社(経営トップ)の関与 | 労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること。 |
| 行動② | 発注者側からの定期的な協議の実施 | 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。 |
| 行動③ | 説明・資料を求める場合は公表資料とすること | 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重すること。 |
| 行動④ | サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと | 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適切な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させること。 |
| 行動⑤ | 要請があれば協議のテーブルにつくこと | 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。 |
| 行動⑥ | 必要に応じ考え方を提案すること | 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。 |
受注者として採るべき行動/求められる行動の主な内容
| 行動① | 相談窓口の活用 | 労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、中小企業の支援機関(全国の商工会議所・商工会等)の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を収集して交渉に臨むこと。 |
| 行動② | 根拠とする資料 | 発注者との価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いること。 |
| 行動③ | 値上げ要請のタイミング | 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回などの定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。 |
| 行動④ | 発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示 | 発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮すること。 |
発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動の主な内容
| 行動① | 定期的なコミュニケーション | 定期的にコミュニケーションをとること。 |
| 行動② | 交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管 | 価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者双方で保管すること。 |
3.2 調査の実施
公正取引委員会は、価格転嫁に関する各種調査を実施しています。調査結果は公表しています。結果を踏まえ、独占禁止法の禁止事項に該当する行為が認められた発注者に注意喚起文書を送付したり、多数の受注者に対して協議することなく価格を据え置く行為が確認された事業者名は公表したりしています。
「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」結果の主な内容を見てみましょう。
※この調査結果に関する図表の出典は、いずれも概要版です。
- 発注者・受注者の立場を問わず、労務費転嫁交渉指針について知っていたか否かの割合

- 受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合を、労務費転嫁交渉指針について「知っていた者」及び「知らなかった者」別に算出。指針を知っていた者のほうが、「取引価格が引き上げられた」と回答した割合が高いことが分かります。

- 発注者の立場で、受注者からの労務費上昇を理由とした取引価格の引上げの求めに応じて、価格協議をしたか否かの割合。

- コスト別の転嫁率と、サプライチェーンの段階別の労務費の転嫁率。一次より二次、二次より三次と段階が進むにつれて、価格転嫁が進んでいないことが分かります。

3.3 現場の声
価格転嫁についての事業者の声を見てみると、発注者から進んで価格協議の呼び掛けはしないものの、受注者から価格転嫁の要請があれば協議に応じるとする発注者が存在しています。これは、受注者側から積極的に価格転嫁を要請すれば、価格転嫁が受け入れられる可能性がある、とも言えます。
受注側
- 最高益を出している大企業であっても発注価格を引き上げてくれない。大企業は自社社員の賃上げだけでなく、取引先受注者の賃上げについても発注金額に反映させてほしい
発注側
- 受注者から値上げの申入れがあれば全て受け入れているが、申入れがない限り価格改定は行わない
- 値上げの相談があった受注者とは価格協議をしたが、相談がない受注者については取引価格を据置きとした
3.4 価格交渉の申込様式
「3.1」で紹介した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」には別添として、下記の通「価格交渉の申込み様式(例)」が用意されています。公正取引委員会のホームページからダウンロードすることが出来ますので、申し入れを検討している企業は、参考にしてみてください。

04 相談窓口などの一覧
官公庁などは、価格転嫁に関する相談窓口を設置しているほか、参考になる情報を掲載したウェブサイトや冊子などを公表しています。主なものは以下の通りです。
| 取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 情報提供フォームや相談窓口、各種調査結果などを紹介しています。 |
| 価格交渉・価格転嫁にかかる 取組事例集 | 近畿経済産業局が公表しています。価格交渉における取組に工夫が見られ、かつ効果的である/自社の強みを生かし価値向上への取組を実践し、価格転嫁に好影響を与えている、といった企業の事例が掲載されています。 |
| 価格交渉・転嫁の支援ツール | 中小企業庁のウェブサイトです。価格転嫁サポート窓口、価格転嫁検討ツール、取引適正化に向けた発注側企業の取組例などを紹介しています。 |
| 価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果 | 中小企業庁は、毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」に合わせ、受注企業が、発注企業にどの程度価格交渉・価格転嫁できたかを把握するための調査を実施しており、その結果を公表しています。 |
| 価格転嫁に関する支援情報 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しているサイトです。企業の取組事例やQ&A、関連ニュースなどを掲載しています。 |
| 【改訂版】中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック | 中小機構が公表しています。価格交渉を行う上で、中小企業が押さえておくとよいポイントなどを紹介しています。 |
| 下請かけこみ寺 | 中小企業の取引上の悩み(企業間取引)を相談員や弁護士が受け付けます。国が全国48か所に設置しています。 |
| よろず支援拠点 | 中小企業、小規模事業者の経営上の相談に対応するため、国が全国に設置した無料の経営相談所です。 |
| 地方公共団体の官公需に関する相談窓口 | 地⽅公共団体から受注した中⼩企業等からの価格転嫁等に関する相談を受け付ける窓⼝一覧です。 |
| 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト | 経済産業省などが推進している制度で、企業がサプライチェーン全体での共存共栄を目指すため、「価格転嫁を含む望ましい取引慣行」を宣言・公表するものです。登録企業の検索も可能で、どのような企業が転嫁に前向きな姿勢かを確認することができます。 |
| 東京商工会議所の「価格転嫁ナビ」 | 受注者向けに、価格交渉の進め方や原材料価格の動向、付加価値向上のヒントなどを整理したポータルサイトです。 |
05 適切に行われない場合の弊害
適切な価格転嫁の必要性や、実現へ向けた取組などを紹介してきました。ここで改めて、適切に行われない場合の弊害について考えてみたいと思います。
5.1 中小企業に忍び寄る「疲弊と停滞」
中小企業は地域での雇用創出やサービス提供を担う、経済の基盤的な存在です。適切な価格転嫁が行われない場合は、以下のような悪影響が考えられます。
- 利益の圧迫
- 賃上げが困難となり、人材が流出
- 設備投資や研究開発の停滞
- 資金繰りの悪化と廃業リスクの増加
こうなると、中小企業は成長への意欲と活力を失い、疲弊と停滞のスパイラルに陥ります。日本経済全体の成長の鈍化にも直結する深刻な問題です。
5.2 大企業の競争力低下を招く可能性
もし、下請けにコストを負担してもらえば得だと考えている大企業があるとしたら、それは大きな誤解であり、自社の未来に「負債」を積み重ねているに等しい行為です。中小企業が疲弊し、経営難に陥ることで以下のような事態を招き、巡り巡って大企業自身の競争力をむしばむからです。
- 安定供給が途絶え、自社生産に支障が生じる
- 自社製品の品質低下につながり、信頼と競争力を失う
- ESG評価の低下:近年重要視されているESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:企業統治の三つの要素を考慮した経営を行う企業)投資の観点から、サプライチェーンにおける不公正な取引は評価を大きく下げる要因となり、資金調達にまで影響を及ぼす可能性があります。
以上のように、適切な価格転嫁を行わないことは短期的なコスト削減になったとしても、長期的な視点では競争力低下につながる可能性があるのです。
5.3 まとめ-適切な価格転嫁が促す共創
「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」結果からは、発注側と受注側、双方が工夫を凝らしている様子もうかがえました。まずは、発注側の取組を見てみましょう。
- 価格転嫁については、社長の強いトップダウンにより行ってきた。特にこれからは労務費の転嫁に応じていく旨を社内外に発信しており、取引の適正化に取り組んでいる。
- 受注者に対し、取引価格引上げ要望の有無を確認したところ、公的指標を超える引上げ率を提示された。精査の結果、公的指標を超える分については過去の市況との乖離分であり妥当と判断し引き上げることとしたが、一度に受け入れると経営上の負担が大きくなることから、受注者と協議の上、まず6割を今年度に反映し、残りの4割を次年度に反映する方法で、2年間かけて市況との乖離を解消することとした。
- 受注者との共存共栄を図るべく、二次受注者やその先の受注者の存在を意識した価格交渉を行っており、一次受注者に対して二次受注者やその先の受注者のコスト上昇分も含めた転嫁要請をするよう声掛けしている。
一方、受注者側も、ただ訴えるだけではなく、根拠を踏まえた交渉姿勢が重要です。以下に紹介する事例はいずれも、公的な指標や制度を活用することで、発注者の理解を得ることにつながった取組です。
- 当社が加盟する団体では、国、県などの行政機関、商工会議所・商工会と連携を図り、価格転嫁に関する講習会を開催していることから、これに積極的に参加し、価格交渉の参考とした。講習会での説明を踏まえ、最低賃金等の公的指標を根拠として発注者に値上げを打診し、価格改定の必要性を繰り返し説明した結果、価格改定が実現した。
- 労働者派遣に係る賃金の相場と最低賃金との間に乖離があることから、都道府県労働局に赴き、発注者との価格交渉の際に活用できる数値・資料等について相談の上、価格改定の依頼文書に最低賃金の引上げ状況を盛り込み、価格引上げの根拠とした。その結果、要請した額の8割程度は引き上げてもらえた。
適切な価格転嫁は、サプライチェーン全体を活性化し、発注する側と受注する側が互いの成長を加速させる戦略であり、企業間の共創を促す重要なステップと言えるのではないでしょうか。
▼正会員登録で見れる!アーカイブ動画配信中▼
▼ BizRizeでは、無料相談を行っております! ▼
▼ 補助金情報を毎週お届け!無料メルマガ配信中です ▼

BizRize事務局
ヒト・モノ・カネに関する経営資源を、効率よく活用できるプラットフォーム「BizRize」を運営。毎週木曜に経営者向けの勉強会を開催し、補助金や資金調達に役立つ情報を無料メルマガで配信中!